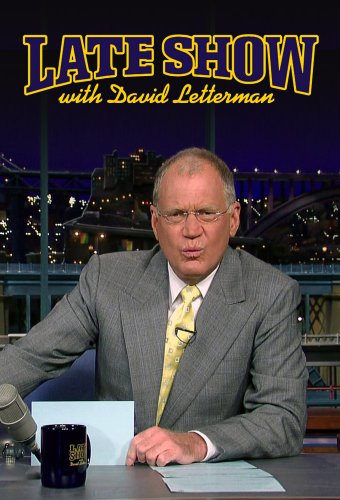いつもは政治家やジャーナリストなど、絶えず眉間にしわを寄せているような人たちが私の周囲には多いが、今日ばかりは少しだけ華やかな世界をのぞいた。
国際短編映画祭「ショートショート・フィルムフェスティバル&アジア」の授賞式に招待されたので、胸にポケットチーフを入れて出かけてきた。渋谷のヒカリエ・ホールには 普段、映像で観る芸能人があふれていた。
会場に入る前に、四畳半くらいの広さがあるエレベーターに乗った。そこでまず、叶姉妹の妹と乗り合わせた。もちろん知り合いではないが、なんとなく視線を投げてしまう。 大きなサングラスをしているが、どこをどうかくしても叶姉妹であることは隠せず、思わず頬がゆるんでしまう。
自宅で招待状を眺めたときに、藤原紀香、相武紗季といった名前が読めたので、フンフンと思っていると、妻が韓国人俳優チョン・ウソンの名前を見つけて「写真撮ってきて」。夫婦そろってミーハーだったことがよくわかった。
案内状には書かれていなかったロックバンドGlayや千原ジュニアといった多くの芸能人がいて、少しだけ別世界を体験することになった。
授賞式では数本のショートショート・フィルムが上映され、最優秀作品賞にはイラン人監督の 『キミのモノ』が選ばれた。
ただ、会場を後にして仕事場にもどる途中に「別世界の魔法」はすぐに解けてしまった。(敬称略)
左から冲方 丁(うぶかた・とう)、藤原紀香、奥田瑛二、レザ・ファヒミ監督、河瀬直美、チョン・ウソン